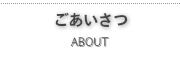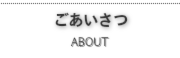断片的な思い出は自分にとって結構重要だったりする。思い出しては瞬間瞬間メモしていこうと思う。自分ごときがやることではないが、何かの参考ししてもらえれば幸いであります。
![]()
名前

娘が高2の春、配達用の軽自動車で学校に迎えに行った帰り道、隣の助手席から娘がこう質問してきた。「ねぇどうして、うちの名前を ゆき って名づけたの?」。答えにつまった。名前の由来はあまりにもバカバカしいほど感傷的な理由であったため、いままで娘に話したことはない。というか誰にも話したことがない。もっと大きくなってからと思っていた。人の感傷をバカにしないような、そんな許容量の大きい年齢になるまでと思っていた。高2の娘っこにウエットな話は一笑されるだけだからと躊躇してると、その時娘から意外な言葉が返ってきた。「私はゆきという名前を非常に気に入っている。今も昔も、その名前でいることがとてもうれしい、もし私がこの名前ではなくて、クラスにゆきという名前の子がいたら、その子のことをとても羨ましく思ったと思う。」そんなめずらしくしおらしいことを言ってきた。んじゃ、ま、いいかなぁと思って、バカにされるのを覚悟でお父さんは話し始めたのだった。一種の告白めいた滑り出しになった。お父さんが中2の時の話だ。国語の教科書にのっていた詩が元になっている、題名は忘れた。問題形式になっていて、雪が深深と降る中、兎が耳を傾けている(ように見える)。さて兎は何を聞いているのでしょうという設問だった。答えは「雪の音」だった。雪が雪面に不時着する時、カサッという音を聞いているのではないだろうか。そのような事を書けば正解のようだった。お父さんは間違えたのを覚えている。しかしその時、動物の方が人間よりずっとずっと優れている事を知り驚いたのだのだ。確かにあの大きな耳の兎には聞こえているのかもしれない。人間には聞こえない音が聞こえている。その兎の詩のことがずーっと頭ん中に残っていて、君が生まれた時、なんか書き残して置かなきゃの気持になり、よせばいいのに柄にもなくお父さんは詩を作った。臆面もなくその詩をここで披露する程、厚顔無恥ではないつもりなので辞退させてもらおうと思うが、内容はだいたいこんなだった。君が生まれた時、ざわざわが無くなったように思う。若いころあんなに心がざわざわして多分苦しかったと思う。苦しくて、ざわざわがいやで喧騒とざわめきの中に身を置いたこともあった。でもざわざわが収まることはなかった。しかし心は静かになった。君の誕生はお父さんの心をおちつかせてくれた。赤ん坊の寝顔というのは大人を強くする。だから大人はそのお礼に優しさをプレゼントする。赤ん坊は命に満ちている。だから我々だけを頼ってくれるそんな風に流れる静かな時間に心をあずけることができる。君が居てくれるから、ゆきの音が聞こえる。聞こえるくらい静かな気持になれる。そんでもって、僕らは君のそばにいる。ゆきの音が聞こえるまでだ。雪面に不時着する雪の音が聞こえる日まで我々大人はいつも君のそばにいる、、、、という、そんな内容だった。要するに、人はうんとうんと静かな気持になった時、ゆきの音が聞こえるのかもしれない。ゆきの音が聞こえるくらい静かな気持の持ちぬしになって欲しい。そんな理由で名前をつけた。しゃべり終わった後、おそおそる隣の娘の方を見た。思春期特有のきつい嘲笑のまなざしが待っていると思った。お父さんは身がまえをした。いい親父が何を熱弁してんだ。自分の顔は失敗したかもしれないという苦渋で歪んでいたと思う。すると娘は進行方向を見つめながらこう言った。「なんでそんな大事なこと今まで教えてくれなかったんだ。」と、、、、、意外だった。意外な答えが返ってきたのでこちらがびっくりする。とりあえずよかった。無邪気にこちら側の心を傷つけられるかと思っていたので、正直ホッとした。土足で踏み込まれたくない部分だったためうまく死守できた格好になった。もしかすると娘の心に一矢届いたかもしれない。するとなぜだかドヤ顔が沸き起こってくる。こんな部分が親父という人種のダメなところなのだろう。しかしドヤ顔を見透かされることもなく、心を読み取られることもなく、そんな運転中であったことが幸いした、表情はいかようにでもごまかせる進行方向最優先の運転中であったことが幸いしたのだ。