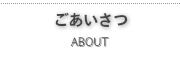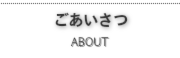断片的な思い出は自分にとって結構重要だったりする。思い出しては瞬間瞬間メモしていこうと思う。自分ごときがやることではないが、何かの参考ししてもらえれば幸いであります。
![]()
夏のこと
 夏のことだった。転校してきてばっかりの数か月がたった頃のことだ。娘が小4の夏頃だった。ある同級生の女の子の誕生会に有希はお呼ばれされた。数人しか呼ばれないようだったのでその中の一人に選んでもらえたことを本人はとても喜んでいたみたいだ。プレゼントするためからと有希はその子が喜びそうな小物を買いに行ったりし、そして当日に備える。だがしかし当日の朝のことだ。学校でその子にこう言われたのだった。「やっぱり有希は無理。ごめん」。そう言われたらしい。学校から帰ってきた有希に「これから誕生会に行くんだろ」というお父さんの無神経な質問に、「行けなくなった」ことを正直に報告してきた。お父さんはただただ沈黙する。それから、それから娘はしばらくして隣の部屋でなんだか遊びだしたのだった。昔むかし小学校に上がる前の頃、毎日のように遊んでいたシルバニアの玩具を引っ張りだしてきて、そしてままごとを始めた。ただひたすらままごと遊びに没頭する。そのうち有希の目に涙が湧いてくる。それはくすぐるように頬をつたう。くすぐる訳のわからないもの、それは涙なのだが、虫が顔にしつこくへばりつこうとするのを嫌がるように素手でもってぬぐおうとする。ぬぐってもぬぐってもあふれ出てくる。どうするこども出来ない。家族に根掘り葉掘り聞かれるのが嫌なのか声を出さず黙ったまま泣いていた。そんな様子だった。自分をコントロールできないでいる娘がそこにいた。でも表情はというと意外にも泣き顔という訳ではない。むかし、うんと小さい頃、ままごとに没頭する当時のなつかいしいあの穏やかな顔つきそのままだったように思う。そういえば娘は昔からあんまり泣かない子だった。そんなことをあらためて思う。あんなに涙を流したのは後にも先にもこの時だけだったのではないだろうか。そんな出来事があってかどうかは分からないが、その後、娘はますます泣かない子になっていったように思う。
夏のことだった。転校してきてばっかりの数か月がたった頃のことだ。娘が小4の夏頃だった。ある同級生の女の子の誕生会に有希はお呼ばれされた。数人しか呼ばれないようだったのでその中の一人に選んでもらえたことを本人はとても喜んでいたみたいだ。プレゼントするためからと有希はその子が喜びそうな小物を買いに行ったりし、そして当日に備える。だがしかし当日の朝のことだ。学校でその子にこう言われたのだった。「やっぱり有希は無理。ごめん」。そう言われたらしい。学校から帰ってきた有希に「これから誕生会に行くんだろ」というお父さんの無神経な質問に、「行けなくなった」ことを正直に報告してきた。お父さんはただただ沈黙する。それから、それから娘はしばらくして隣の部屋でなんだか遊びだしたのだった。昔むかし小学校に上がる前の頃、毎日のように遊んでいたシルバニアの玩具を引っ張りだしてきて、そしてままごとを始めた。ただひたすらままごと遊びに没頭する。そのうち有希の目に涙が湧いてくる。それはくすぐるように頬をつたう。くすぐる訳のわからないもの、それは涙なのだが、虫が顔にしつこくへばりつこうとするのを嫌がるように素手でもってぬぐおうとする。ぬぐってもぬぐってもあふれ出てくる。どうするこども出来ない。家族に根掘り葉掘り聞かれるのが嫌なのか声を出さず黙ったまま泣いていた。そんな様子だった。自分をコントロールできないでいる娘がそこにいた。でも表情はというと意外にも泣き顔という訳ではない。むかし、うんと小さい頃、ままごとに没頭する当時のなつかいしいあの穏やかな顔つきそのままだったように思う。そういえば娘は昔からあんまり泣かない子だった。そんなことをあらためて思う。あんなに涙を流したのは後にも先にもこの時だけだったのではないだろうか。そんな出来事があってかどうかは分からないが、その後、娘はますます泣かない子になっていったように思う。
少人数の学校から大勢の学校へ転校してきた娘のカルチャーショックみたいなものだった。これからいろいとあるだろう。悪いが父親は沈黙するのが一番だ。
転校してきて、大勢の学校に通う娘に対して大げさにもこう思った。もしかして、もしかしてようやく娘は人の世に放たれたのだろうか、水の勢いに揉まれ削られていく川の中の石ころのように、勝手に傷つき丸みを帯びていく。もはや親の出る幕ではない。そんな感じがしてしょうがないのだった。でも娘はなんだか人生というものを始めたらしいのである。夏のあの日、涙が止まらなかった小4の夏、たくさんの涙と引き換えに何かを学んだのだろうか。悲しい思いは自分で処理しなければならない、親に救いを求めてもしょうがない、そんなこんなの娘の目は赤く、眼底出血のように真っ赤な目をしていて、赤い目のまま前方を見据えている姿は、多少頼もしさも感じられる。人生を始めたらしいと感じたのは親馬鹿のそれではなく、もう親の手の届かない所で何かが起っている。手を貸したくても貸せない。本人と本人の運にまかせるしかないのだろう。娘の涙に自分勝手なさみしさを感じてしまったのである。知らんぷりをせればならないことは情けないというよりさみしいという感傷であったよう思う。しかし、しかしだ。なんだかほんのりだが実はうれしかったのである。世の親の気持ちを少しだけ理解できたのかもしれない、そんな夏の出来事だった。