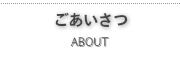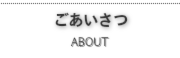断片的な思い出は自分にとって結構重要だったりする。思い出しては瞬間瞬間メモしていこうと思う。自分ごときがやることではないが、何かの参考ししてもらえれば幸いであります。
![]()
急な階段
 今でも思い出す。
今でも思い出す。
オンボロな軽のワンボックスカーに4歳くらいの子供を助手席に乗せて運転しているお父さんを見ると自分の当時を思い出す。
娘は完全なお父さんっ子だった。当然なことだが父子家庭の頼り処はお父さんしかいない訳なのだが、いつでもどこでもくっついてきた。金魚の糞だった。配達でも市場の買い付けでも便所でも。仕事に子供を連れていくのははばかれたのだが、そんなことを言ってられない。お客さんと接する配達先へも連れていった。子連れ納品業者として知られるようになった。お客さんには最初とまどわせてしまった。どう対応していいかわからなかったようだ。しかししかしだ、段々慣れてきてくれたのか大目に見てくれるようにる。もし仕事に支障がでるならそれはそれで仕方がない。契約を打ち切られるおそれもあったが、それでもしょうがない。しかし、中には、「娘さんをまた連れてきてねー」と言ってくれるお客さんもでてきた。お菓子を用意してくれているお客さんも出てきた。お菓子問屋さんに仕入れにいくと担当者は娘にどっさりお菓子のお土産をくれることも、ありがたかった。
しかし、一番つらかったのはとある病院の給食材料の配達だった。毎日野菜や食品あわせて15kくらいの荷物になる。厨房は3階にある。業者なので患者さん用のエレベーターは使えない。せまい病院なので階段というより梯子に近い。あきらかに建築基準法違反というか消防法に違反しているような急傾斜だった。そこを娘をかついで荷物を3階まで運ぶ。その登りの作業がまぁゆるくなかった。どうやったかというと。「絶対手を離すんじゃないよ!怪我するからね!」と言って娘をまず自分の前側の首にしがみつかせる。両肘で娘の臀部というか全体をなんとなく支える。そして肘から先の腕で荷物を持ちその状態で3階まで登る。娘は危険な状態であることを理解しているためかお父さんの首に満身の力でもって必死にしがみつく。そして一段一段階段を登っていく。やっとこ3階に近づく頃だ。たまに涙がにじみ出てきた。俺は何をやってるんだろうというような情けない気持ちが多少まじっていたかもしれない。確かに体は辛くてヒイヒイ泣いている。だが不思議と心は喜んでいたようだった。こんなことをやっている自分がうれしかったのである。こんなことをやれている自分がうれしかった。涙の主(ぬし)はよろこびのようであった。
娘はここの病院の配達に行く時は必ず付いて行きたがった。危険な感じが子供にとって冒険心をくすぐられて楽しかったのかもしれない。でも必死になって自分に抱き付いてくる娘にこう思った。誰かに抱き付きたいのだ。娘は誰かに抱き付きたかったのだ。病院の配達の時だけは遠慮なく抱き付ける。娘にとって親の首にぶら下がるように思いっきり抱きつくことができる絶好のチャンスだったのだと思う。目をつぶり、必死にしがみつくように抱き付いている娘を見るたび、今まで以上に子供を愛おしく思えるようになっていった。そしていろんなものがあふれ出てくる。思いやら感情やら愛おしさやら、人は総じてこのあふれものを愛情と表現するのだろう。段々あふれるものは日増しに強くなっていく。大げさに言えば人格が崩壊するほどだった。自分という人間が崩壊するのではないかと思うほどに何かが大量にあふれくる。そのあふれでる思いに対しなんとかうち勝ち敢然と立ち向かい、セーブすること、それをうまいことコントロールすること、それが自分にとっての子供との接触の時間になっていった。世のお母さん方の子育ての喜び、世に言う子育ての喜び、その喜びの源流とはこういうものなのだろう。そんなことをこの時期、少し理解できたように思う。
自分はこう思う。愛情とは得体がしれない。人が崩壊しかけるほどのエネルギーのようなものだと思う。子育てとは、子供を育てるということは、もしかすると大量のエネルギーを食い止めながら、ちょっとずつ安定供給するための調整弁やトランス、灌漑用のダムような働きによく似ている。しかし、このままではいけないということも同時に強く思った。このままでは子供を甘やかしてしまう。猫可愛がりしてしまう。このままでは子供がダメになる。自分の思いなどとというのはバレてはいけない性質のものだった。どうしたら良いのか、そして考えたあげく、無骨な性格の自分にできるたった一つの方法、その方法は決してほめられた代物ではなかった。それはあふれ出るものを封じることであり、そして、自分の心に鬼を育てること。厳格な父親になること、理不尽で無神経になること、無理解で石のように固い頭の持ち主になること、残念ながらそんなやり方しか自分にはできなかったように思う。それは子供のためというより、今思えば、自分への偽装のためだったように思う。偽装に必死にならざるを得ない程、自分のせいで子供がダメになるのはイヤだった。ダメのなることが恐ろしかった。なので自分にとっての子育てとは、正体がバレないように日々ビクビクしながら生活をする、そんな犯罪者のようであった。